BS1スペシャル「山中伸弥が聞く 新型コロナ 〜3人の科学者+1人の医師との対話〜」②
- AKIKO SAKAI

- 2020年6月24日
- 読了時間: 9分
更新日:2020年6月25日
2回目の注目点は
① 自然免疫系は訓練できる「訓練免疫」
② 訓練免疫にはアジュバントが有効
③ 患者自身の回復力(治癒力)がベースにある
④ 抗体にはウイルスを殺す善玉抗体だけでなく、ウイルス感染を促進する悪玉抗体もある
つまり自然免疫は訓練することができ、そのためにはアジュバントが有効だ!っていうことです。
出演(前半)
山中伸弥 京都大学iPS細胞研究所 所長・教授
宮坂昌之 大阪大学名誉教授 免疫学の第一人者
大曲貴夫 国際医療研究センター病院 国際感染症センター長 感染症専門医
ナレーション:新型コロナウイルスに感染しやすいかしにくいか、それがはっきりわかる日は来るのでしょうか。今は皆、同じように気をつけるしかないようです。
そして、山中さんは「子ども」に注目。
山中先生:人による症状の違いという意味で、もう一つ不思議なのは子どもさんです。おそらく、子どもは軽症、無症状が多いのでは。これがなぜかが不思議で、宮坂先生が言われた他のコロナウイルス「普通感冒」に子どもはしょっちゅうかかっているので、弱いながらも何か免疫を持っているんじゃないかという可能性も考えたりするんですが、どうでしょうか?
宮坂先生:鼻風邪のコロナウイルスによってできた抗体は必ずしも新型コロナウイルスを殺してはくれない。ですから、前に鼻風邪コロナにかかってたということが子どもさんがなりにくい原因というよりは、恐らく他のところにあるのではないかと私は考えています。
その一つが、子どもさんは学童期、恐らく小学校を卒業するくらいまでの間にたくさんのワクチンを打つ。ワクチンは本来は特定の病原体に対する免疫を上げるんですが、その免疫効力を上げるために通常ワクチンの中には、半数くらいのワクチンにはアジュバントという免疫増強物質が入っている。この免疫増強物質は何をしているかというと、自然免疫を刺激している。自然免疫系を刺激することによって獲得免疫を動きやすくするというのが「アジュバント」、免疫増強物質なんですが、子どもさんたちはこの「アジュバント」の入ったワクチンを何度も受けていますので、少なくともそのワクチンを受けた直後、あるいは一定期間の間は大人に比べると免疫系が少し高まった状態になっている可能性が考えられます。これは、実は今までの免疫学の常識では「自然免疫系は一度見たものを覚えてない」「刺激を受けてもすぐ元通りに戻ってしまう」と言われていたんですが、最近のオランダのグループの報告を見ますと、実際はそうではなくて、自然免疫系が一度、例えばワクチンなんかで刺激すると1年以上その効果が上がった状態が続いている。そういう免疫のことを「訓練免疫」「trained immunity」「自然免疫系は訓練すれば強くなる」という言い方をするんですが、数日とか1週間とか月単位ではなくて、もっと長くって、自然免疫系というのは一度刺激されるとその効果が続く。子どもさんがかかりにくい理由というのは、もしかするとそのようなあらかじめいろんなもので免疫系が刺激を受けているということが一つの理由なんではないだろうかと考えられるわけです。
山中先生:宮坂先生のお話をお伺いすると、どうしてもBCGワクチンのことを考えてしまうんですが。
ナレーション:山中さんがBCGワクチンに関心を寄せるのは、それが「ファクターX」なのではないかと考えているからです。日本の感染者や死亡者が欧米に比べ少ないことの理由を、山中さんはみずからのサイトでその候補を複数挙げています。BCBの他にも「生活文化」「遺伝的要因」「何らかのウイルス感染の影響」など。この「ファクターX」を明らかにすることが今後の鍵になるといいます。
山中先生:ここがなぜかというのも、今後、長期の対策が必要ですので、考えていく上で非常に必要だと思います。一つはBCGワクチンの影響もありえますでしょうか?
宮坂先生:これはあるようにも見えますし、そうでないと思われるようなエビデンスもあります。BCGを常に国民にここ何十年もの間接種している国においては、ほとんどアジアなんですが、いずれも死亡率が低い。重症化率も死亡率も低い。一方、過去にBCG接種はやっていたけれど10年以上前に止めてしまった、主にヨーロッパ諸国ですけれど、死亡率が相対的に高い。例えばイタリアとか、ほとんどやっていないアメリカも非常に高い。そういう相関は確かにきれいに見えるんですが、例外もあって、例えばオーストラリアは私が知る限りにおいてはもう20年以上も前にBCGを止めていますが死亡率は非常に低いです。感染者数も低いし死亡率も低いです。フィンランドも。フィンランドとオーストラリアは必ずしもはまらない。とすると、BCGはひとつのファクターかもしれませんが、それ以外のファクターがたくさんあるだろうという気はいたします。
山中先生:統計というのはよくだまされるというのも事実でね。相関関係があるからといって因果関係があるかは気を付けないと。ただBCGの場合は自然免疫をトレーニングするという意味で理論的にももしかしたらありえる話かもしれませんので、今後も注意をしていく必要があると思っております。
ナレーション:さて、次の質問はこれも気になる薬について。
山中先生:治療薬のお話をお伺いしたいと思います。「アビガン」「レムデシビル」「イベルメクチン」「フサン」「アクテムラ」こういったものが期待されておりますが、大曲先生、実際に使われたことのある薬というのはこのうちどれになりますでしょうか?
大曲先生:うちの施設でまだ使われたことのないのはイベルメクチンだと思いますが、それ以外は使っています。
山中先生:それなりに有効な可能性があるという印象を持たれていますでしょうか?
大曲先生:それがですね、本当に難しくてですね。やはり、この病気が多くの方は自然経過の中で軽快されていくというところがベースにあるものですから、それによって物事が見えにくくなっているなっていうのはすごく思います。つまり、お薬を使いながら経過の中で良くなっていく方はたくさんいらっしゃいます。そこだけ見ていくと薬のせいだって感性的には思いかねないんですが、ものの見方としては偏りがあるだろうと。一方で、ある程度以上の重症度の方で、さまざまな抗ウイルス薬がある中でそれらを使われても抑えが効かなくて悪くなっていく方がいらっしゃるのも現実。わからないというのが正直なところです。
山中先生:薬の開発の場合は、一番いいやり方は二重盲検試験で、コントロール群を設けて偽薬を投与して、投与する医師も服用される患者さんもどちらか分からないという試験が一番、今のようなバイアスを除外するいい方法だと思うんですが、今回のような新型コロナウイルスで一歩間違えると死に至る可能性がある病気のときに、二重盲検試験は実際問題として行うのは難しいんじゃないかなと思うんですけれど。
大曲先生:医師の心情、患者の思い、きわめて難しいと思いました。素朴な我々の思いとしては効く薬があるのだったら使いたいというところにまず来ると思いますし、実際、私も1月以降はそういうアプローチをしてきています。ただ、少ないながらの経験を重ねる中で見えてきたのは、可能性のあるお薬はいくつもあるんですが、結局、効いているかいないか、まったくわからないというところに戻ってきたんですね。そこでやはり、二重盲検の意味はあるんだなと改めて思うようになりました。最初は、本当の正直なところを言いますと、一番最初の最初のこの病気と初めて出会ったころは、そういうことをやっている余裕はないんじゃないかという思いが先に立っておったんですが、少し経験を積んでいく中で、やっぱり二重盲検試験がないと先に進めないと思うようになったというのが正直なところです。それからは腹が据わったんです。
山中先生:わかりました。これは本当に現場で実際に診療に当たっておられる先生も大変な状況だと思います。こういったアビガンとかレムデシビルは、基本的にはウイルスの増殖を抑える薬、侵入も抑えるということで、どちらかというと早めに投与したほうが理論的に考えるといんじゃないかと思うんですけれど。
大曲先生:う~んとですね、まだ正直よく分からないなと思っています。ただ、薬の開発の端くれとして加わった者としては、やはり肺炎にならないようにしたいというのが一番最初でしたので、恐らく病気の最初の段階でウイルス量もそれほど多くない段階でお薬を使うということは最初に考えとして立っていきました。ただ、いくつかのお薬をその状況で使ってみたんですけれど、我々が一例一例の経験で診るレベルではものが見えてこないなと思いました。そこもやはり、二重盲検になるようにしないとクリアに物事は見えてこないと思っています。ただ、ある程度の重症の方は少し知見が揃ってきています。恐らくそういう方々は一定量、もう体でウイルスが抑え込まれずに増えてしまっている方ではなかろうかと思っています。そういう方々にしっかりと抗ウイルス薬を使うというのは結果的にウイルスの増殖自体を抑えていって患者さんの状態をいいほうに持っていくような印象は持ってはいます。そこは根本的な事実として大事だと思います。
ナレーション:今、世界で注目されているのは、新型コロナから回復した人の血液の一部、血漿を投与する治療法です。
山中先生:海外ですけれど、回復した方の血漿を重症の方に投与する。少ない報告例ですけれど、それなりの効果が見込まれると。理論的にも他の感染症にもよく使われてきた方法だと思うんですが。
大曲先生:MERS、SARS、エボラ出血熱、この治療は使われてきています。日本でも回復者血漿が使えないかの検討は始まっていると聞いています。
宮坂先生:免疫学的なことから、この新型コロナの場合、SARSでもMARSでもそうだったんですが、抗体が出来ているときに必ずしもウイルスを殺す抗体とは限らない。無理に抗体を作らせるといわゆる悪玉抗体、すなわちウイルスの感染を促進してしまうような抗体ができることも中にはあります。重症度の高い人ほど抗体を作っているなら、もしも抗体が善玉だけだったら抗体が出来てきたら症状が治まってくる。あるいは症状の軽い人ほど抗体が多いというなら話が分かるんですけれども、重症例をみると抗体が増えていっているが症状も悪くなっている。こういうケースだと善玉抗体も出来ているかもしれないけれど悪玉抗体も一緒にできている可能性がある。回復した人から血液の液体成分(血漿)を入れればいいか、難しいところです。特に、この病気の場合には再感染というか、治ったと思ってまだ出てくる例もありますよね。ああいう例はおそらく抗体が十分にできていないか、出来ていても悪玉のほうも同時に存在するために善玉と悪玉のバランスで、また病気が始まってしまうようなことがあるかもしれないなと。そういうことから考えると、善玉抗体を作る人を選択的に見つけてドナーの中でも特に優れた人「スーパードナー」から採ると。回復者の血漿というのは有効な治療法となりうるかもしれませんけれど、抗体を作っていたら誰でも供与できるかは違うかもしれないと考えています。






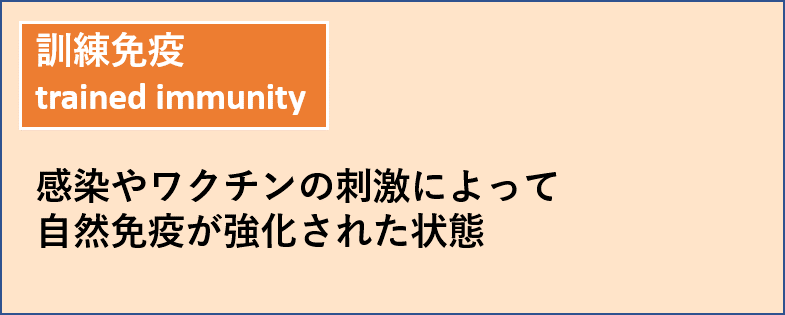





コメント