がんを考える③
- AKIKO SAKAI

- 2023年2月7日
- 読了時間: 2分
遺伝子変異の話をする上で、ゲノム、染色体、DNA、遺伝子を整理しておきたいと思います。

細胞の中にある核には染色体が格納されています。ゲノムとは染色体全部のことを示します。
染色体は、二重らせん構造のDNAがギュ~っと折り畳まれています。
人間は23対の染色体があります。そのうちのひとつ、性染色体は女性がXX、男性がXYですね。
DNAを伸ばしてみると塩基が向かい合って結合していることがわかります。
A(アデニン)はT(チミン)と、C(シトシン)はG(グアニン)と対になります。人間は約30憶塩基対あることがわかっています。
その中でタンパク質を作る情報を持つ配列を遺伝子と呼びます。
遺伝子はゲノム全体の2%にも満たないことがわかり、衝撃を受けました。
残りの部分は「ジャンクDNA」専門的には「非コードDNA」と呼びます。
非コードDNAはタンパク質を作る情報をもたないDNAですが、この中には遺伝子のオン・オフを担うコントロールスイッチや、細胞分裂のときに染色体の数や長さをそろえるのに必要な構造部品などが含まれているそうです。

がんは遺伝子が変異することで起こる病気です。
遺伝子変異がもっとも起こりやすいのは細胞分裂の時。二重らせんが一度解かれて、DNAを複製する時にエラーが生じます。
また、細胞内の活性酸素によるダメージも大きな要因です。
さらに、化学物質や活性酸素など、遺伝子変異を起こしやすいリスク要因はいくつもあります。
しかし、細胞にはDNA修復機能が備わっていることはもとより、タンパク質を作るための遺伝子はゲノム全体の約2%、おそらく非コードDNAに変異が起こっても影響ないことを考えると、「遺伝子」に変異が起こって問題になる確率はどれくらいなのでしょうか?
正常(と思われる)細胞とがん細胞を比較した研究によって、イメージとはちょっと違った風景が見えてきました。






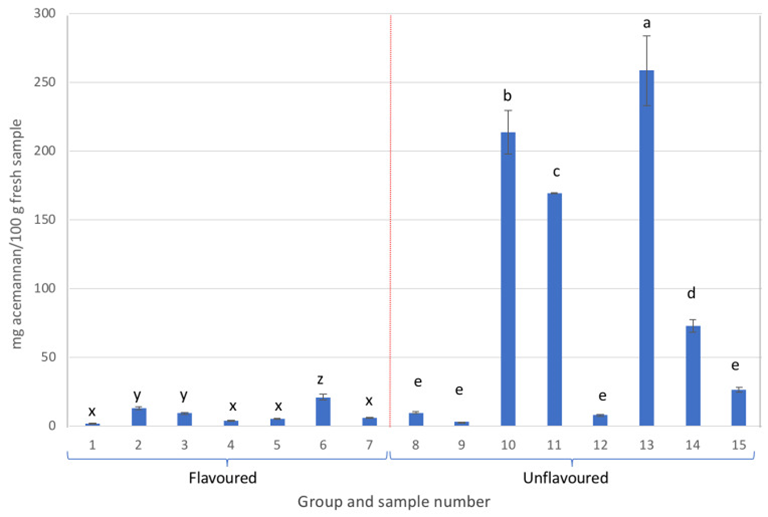
コメント