がんを考える⑤
- AKIKO SAKAI

- 2023年3月10日
- 読了時間: 2分
前回、正常に見える細胞でも多種多様な遺伝子変異が起こっているという話をしました。
当然ながら、がん化した細胞も一律の遺伝子変異ではなく、多種多様な変異が混在しています。
しかし、抗がん剤はある一部の変異に対して開発しているため、すべてのがん細胞に対応できるものではありません。
キャット・アーニー著『ヒトはなぜ「がん」になるのか』には面白い例えが書いてあります。
あるがんの中でメジャーなグループを〇〇会系✕✕組としましょう。
このグループを制圧するために開発した抗がん剤を投与したところ、見事にがんは縮小しました。見かけ上、治療は成功です。
しかし、このグループの脇にいた半グレたちは、抗がん剤の作用機序とは別の変異を持っています。
メジャーなグループがいなくなった今、半グレたちは勢力を伸ばし大きなグループへと成長しました。
最悪なことは、投与した抗がん剤に耐性を持ち、転移能も獲得していることです。
これが、抗がん剤治療をしても再発が起こる一因だというのです。

今までは、遺伝子が変異しているところをデータベース化し、抗がん治療に生かそうという研究が主流でした。
しかし、ひとつのがんでも変異は多種多様であることが分かった今、治療そのものの考え方をアップデートする時期にきています。
上記の例は、実生活に照らし合わせてみると面白いほどよく似ています。
✕✕組や半グレの人たちは、なぜこのような生活になったのでしょうか?
育った家庭や環境の問題でしょうか?
周りの社会はどのように関わっていけるのでしょうか?
体の中に落とし込んでみましょう。
・ひとりひとり(細胞ひとつひとつ)
・集団形成(がんへの成長過程)
・その集団を取り巻く地域社会(細胞間マトリックス、免疫システム)
これらを整えていくことで、予防や治癒につなげていく道を探っていきたいと思います。






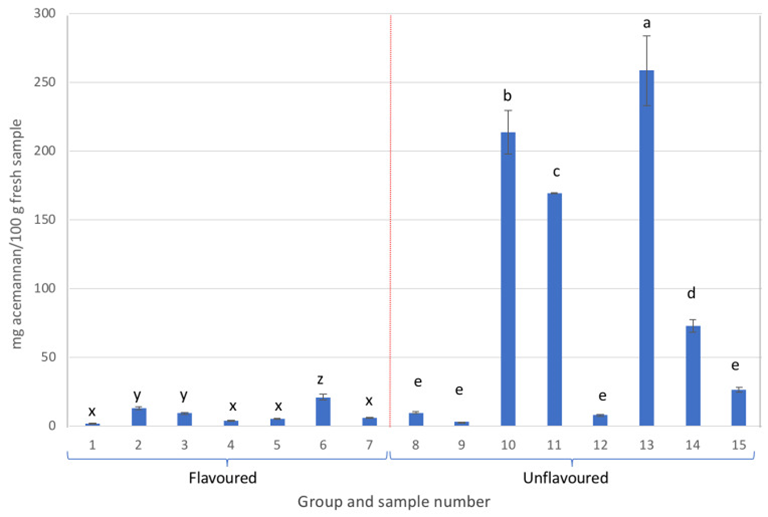
コメント